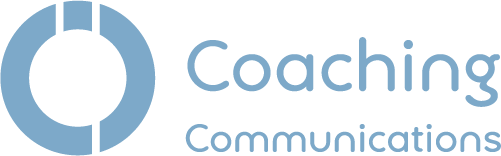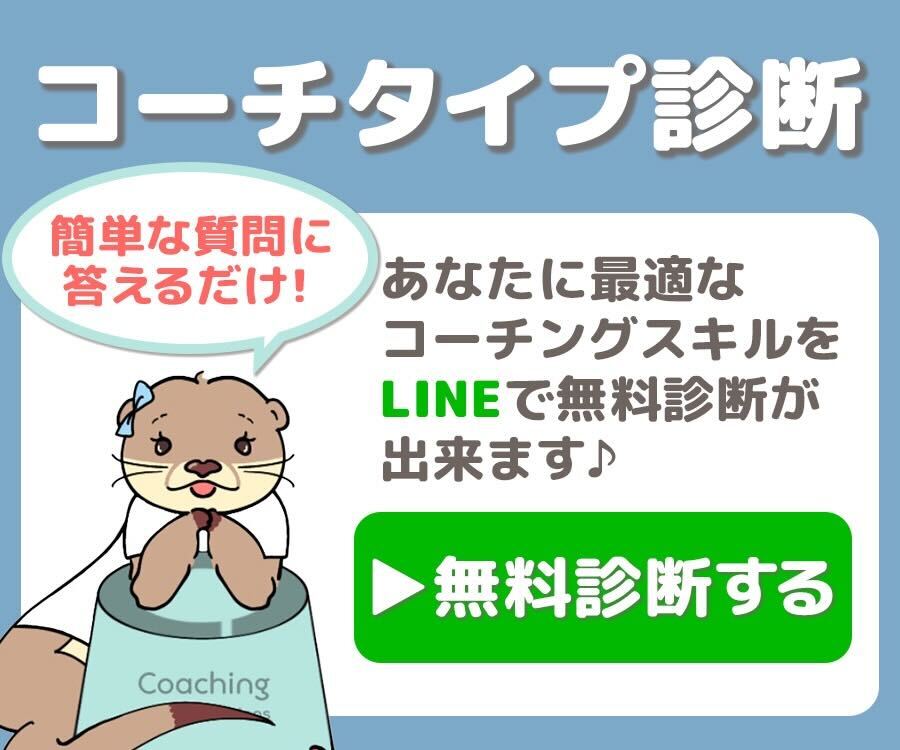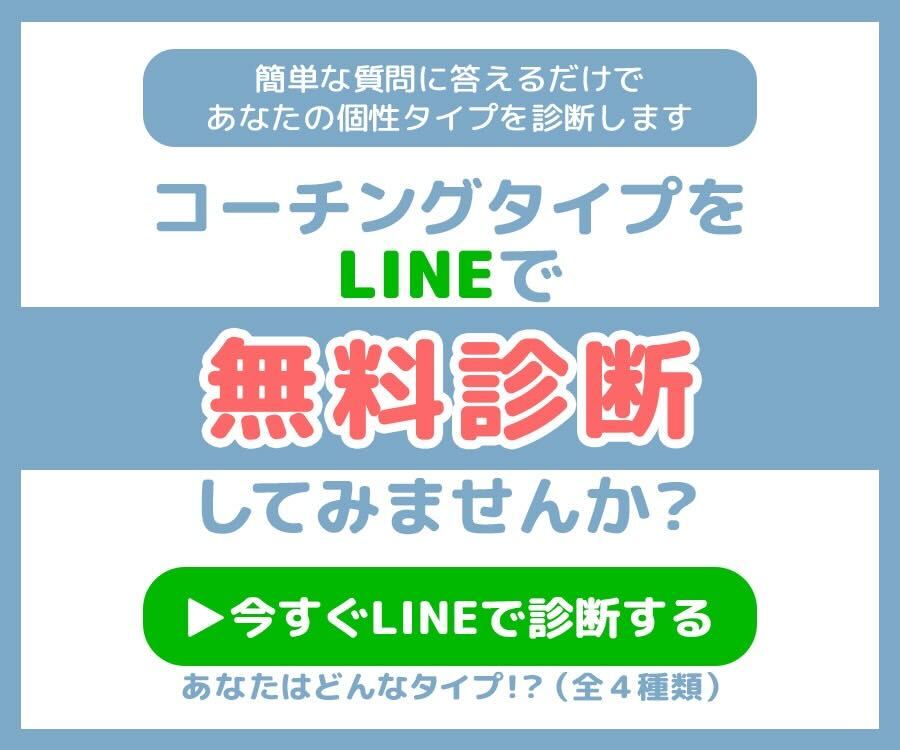プレゼンをする機会というと、「たまにしかない」という人が大半ではないでしょうか。
普段プレゼンに慣れていない人がいざやろうと思うと、なかなか緊張して上手く話せないものです。
プレゼンに自信がない人も多いことでしょう。
しかしプレゼンにはコツがあり、ポイントを押さえることで誰しもプレゼンが上手になります。
プレゼン力はスポーツや芸術などと違って特別な才能も不要ですし、誰しもが後天的に身に付けられるスキルなのです。
この記事では、プレゼン力を身につけるメリットとプレゼンのコツについて解説しました。
「近々プレゼンを控えているが自信がない」という方の参考になれば幸いです。
プレゼン力を身につけるメリット

プレゼン力は様々なシーンで役に立つスキルです。
プレゼン力を身につけるメリットは大きく3つあり、以下それぞれ解説いたします。
論理的思考力が身につく
プレゼンの準備をする際には、論理的思考力が鍛えられます。
なぜならプレゼンの準備をするとなると、物事を多面的に考える必要があるからです。
- テーマとなる課題
- 課題が発生している原因
- 課題の解決策
- 解決策によって予想される効果
これらの内容をまとめたプレゼン構成を考えることで、論理的思考力が身につけられます。
ビジネスシーンで成果につながりやすい
ビジネスシーンにおいて、プレゼン力は直接的な成果につながりやすいスキルです。
どの職種においても話を伝える力は重要であり、プレゼン力を身につけることで情報が整理されて、こちらの意思をより相手に伝えることができます。
特に営業職では、プレゼン力によって相手に行動してもらいやすくなり、成果にも反映されやすいでしょう。
プライベートな人間関係も良好になる
ビジネスシーン以外にも、プレゼン力を身につけることでプライベートな人間関係も良好になります。
なぜなら自分の伝えたいことがより相手に伝わるため、コミュニケーションエラーを防ぐことができるからです。
あなたも人間関係でこんな悩みはありませんか?
- 相手に言ったことが伝わっていない
- 適切な言葉を選べずに相手を怒らせたり、傷つけてしまった
このような悩みが頻繁にある人は、プレゼン力を身につけることで、人間関係が良好になるかもしれません。
プレゼンのコツ(構成編)

プレゼン力を身につけるメリットをご理解いただいたところで、ここから実際に使えるプレゼンのコツを解説していきます。
プレゼンが成功するかどうかは「事前準備で勝負が決まる」と言っても過言ではありません。
プレゼン構成を考える際のコツは以下にご紹介する6点です。
- 聴衆に向けたゴールを明確にする
- 自己紹介・アイスブレイクを入れる
- 最初にプレゼンの概要を伝える
- 話す順番は主張→理由→具体例
- 具体的な数字を使って説明する
- 専門用語を使いすぎない
これらはすべて事前に準備できますので、1つ1つ理解して準備を進めていきましょう。
聴衆に向けたゴールを明確にする
プレゼンにおける構成のコツ1つめは、はじめに聴衆に向けたゴールを明確にすることです。
なぜならゴールを設定しておくことで、プレゼンの内容に一貫性を持たせられるからです。
ゴール設定のコツとして、
- 今回のプレゼンで知ってもらいたいこと
- 聴衆にどういう行動を起こしてほしいか
の2点を明確にしておきましょう。
自己紹介・アイスブレイキングを入れる
プレゼンにおける構成のコツ2つめは、プレゼンの最初に自己紹介やアイスブレイキングタイムを設けることです。
なぜなら、人はよく知らない人の話を真剣に聞こうと思わないからです。
例えばあなたが「悩み相談を聞いてほしい」と頼まれたとして、相手が最近知り合ったばかりのよく知らない人なのか、10年以上付き合いのある親友なのかで、真剣味が大きく変わるのではないでしょうか。
プレゼンする相手にあなたのことをよく知らない人が含まれている場合は、最初に自己紹介やアイスブレイキングを入れて親近感を持ってもらいましょう。
最初にプレゼンの概要を伝える
プレゼンにおける構成のコツ3つめは、最初にプレゼン全体の概要を話すことです。
どんな話をするのかを最初に伝えることで、聴衆は全体像をイメージしやすく、本題の話が頭に入ってきやすくなります。
さらに聴衆から「結局何が言いたいのかよく分からなかった」と思われる事態も防げます。
話す順番は主張→理由→具体例
プレゼンにおける構成のコツ4つめは、1つの内容を伝える際に、主張(もしくは結論)→理由→具体例→主張(もしくは結論)の順番で話すことです。
なぜなら最初に主張や結論を話すことで話の方向性が伝わり、その後に理由や具体例を話すことで説得力が増すからです。
これは文章にも活かせるスキルなので、ぜひ押さえておきたいコツになります。
具体的な数字を使って説明する
プレゼンにおける構成のコツ5つめは、具体的な数字を交えて説明することです。
なぜなら、数字を入れると一気に具体性が増して伝わりやすい内容になるからです。
例えば「明日は早起きをします」と言われるのと「明日は朝7時に起きます」と言われるのでは、後者の方がイメージがしやすいのではないでしょうか。
プレゼンに具体性を出すためのコツとして、数字を入れて説明しましょう。
専門用語を使いすぎない
プレゼンにおける構成のコツ6つめは、専門用語を使いすぎないことです。
プレゼンの際に専門用語が多いと聴衆が理解できず、聞いていて退屈と感じてしまうからです。
あなたも難しい話をされて、眠くなった経験があるのではないでしょうか。
内容にもよりますが、中学生が聞いて分かる内容になっているのが分かりやすいプレゼンのコツです。
プレゼンのコツ(話し方編)

プレゼンが伝わりやすい構成になったところで、次は話し方のコツについてご説明します。
話し方のコツは一朝一夕では身につかないため、事前にリハーサルや練習を通して身につけておきましょう。
プレゼンにおける話し方のコツは、以下の5点です。
- 大きい声でゆっくり話す
- 熱量を出す
- 話すときは、聴衆のうち誰か1人の目を見て話す
- 適度に間を空ける
- 聴衆に質問する
これらは分かりやすく話すコツでもあるため、日頃から意識されることをおすすめします。
大きい声でゆっくり話す
プレゼンにおける話し方のコツ1つめは、大きい声でゆっくり話すことです。
話が聞き取りにくいと、せっかく良い内容を話しても伝わりません。
特に早口の自覚がある人は、1度プレゼンのリハーサルを録音して聴いてみましょう。
客観的に自分の声を聴くことで、改善ポイントが見えてきます。
熱量を出す
プレゼンにおける話し方のコツ2つめは、熱量を出しながら話すことです。
人の心が動くタイミングは、相手から熱量や情熱を感じた時だからです。
熱量を出すポイントとして、ジェスチャーを交えながら話すことをおすすめします。
普段の会話にジェスチャーを使うことはあまりないかと思いますので、リハーサルをしながら練習していきましょう。
話す時は、聴衆のうち誰か1人の目を見て話す
プレゼンにおける話し方のコツ3つめは、視線を聴衆に向けることです。
人は目が合うと、人はより自分に話しかけられていると思って真剣に話を聴くようになるからです。
コツとしては、1秒ずつ視線を向ける人をずらしていくことです。
全員と目が合わなくても構いません。これを繰り返すことで会場全体が話を聴こうとする雰囲気になります。
適度に間を空ける
プレゼンにおける話し方のコツ4つめは、適度に間を空けることです。間を空ける意味は主に2つあります。
- 聴衆にとって理解できる時間が作れる
- 聴衆の意識を引きつけることができる
コツとしては、話が一段落した後と強く主張したい箇所の前に3秒ほど間を空けます。
すると聴衆がこれまでの話をしっかりと理解でき、より意識を引きつけることができるのです。
聴衆に質問する
プレゼンにおける話し方のコツ5つめは、適度に聴衆に質問することです。
一方通行な話があまりにも多いと、聞いていて退屈に感じるからです。
また適度に質問をされると、聴衆はより真剣に話を聴く姿勢になります。
5〜10分に1回程度、聴衆に「どのように思われますか?」「ここまででよく分からなかった箇所はありましたか?」などと問いかけるのがコツです。
まとめ:プレゼンを上手に行うコツ

プレゼンは慣れていない人にとって緊張する場面だと思いますが、今回ご紹介した構成のコツ・話し方のコツで取り入れられそうなものがあれば、ぜひ取り入れてみてください。
冒頭でもお伝えしましたが、誰でも勉強と実践を重ねればプレゼン力を身につけることができます。プレゼン力は様々な場面で使えるスキルなので、学ぶ価値は十分にあるでしょう。
もし1人で学ぶことや実践することが不安であれば、コーチングの体験会に参加することで正しいプレゼンの練習方法やコツを学べます。興味のある方は、1度参加されてみてはいかがでしょうか。