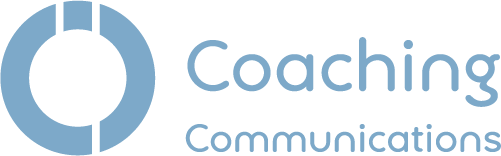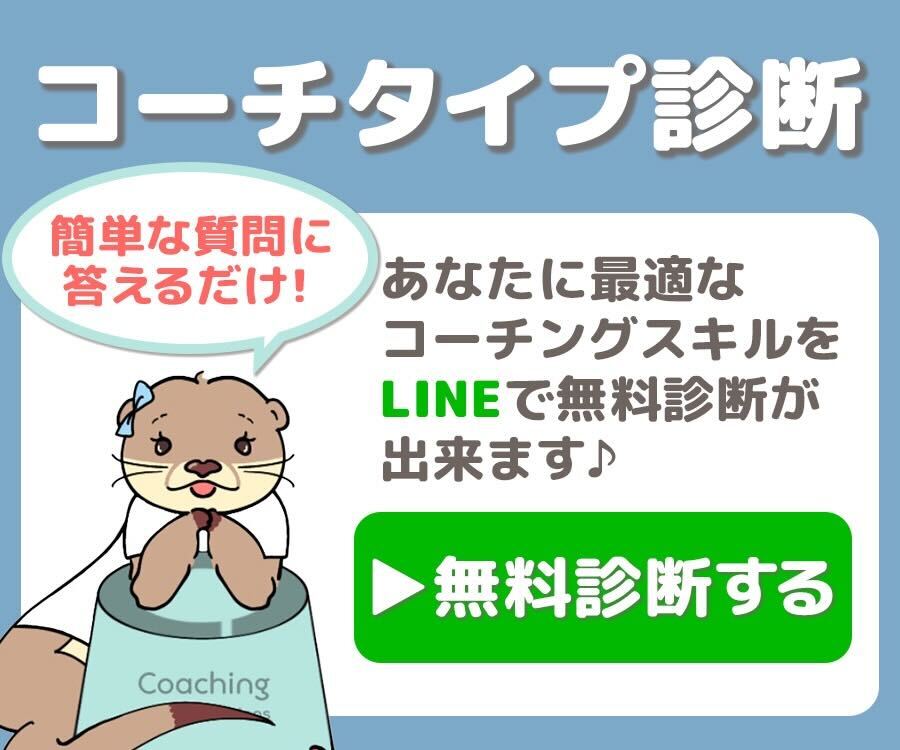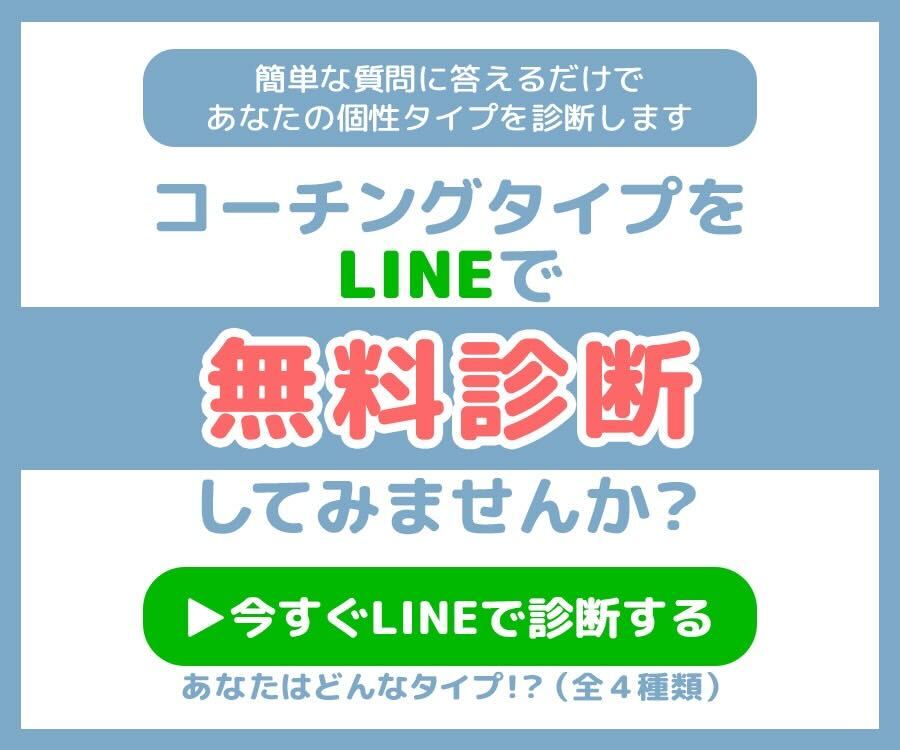皆さんはこう思ったことはないでしょうか?
「人間にはなぜ心があるのだろう?」
心がなければ便利なことはあります。
毎日イライラしなくていいですし、悲しんだり落ち込んだりすることもないです。
心がなければストレスから解放されます。
誘惑に負けることもなければ、サボることもなくなります。
これだけ聞くと無い方が良いように聞こえますよね。
では、なぜ人間には心があるのか。
今回は「心がある理由とその仕組み」についてご紹介します。
「心」はどこにあるのか?

心とはどこにあるんでしょうか?
「心」の研究歴史
そもそも「心」とは存在するのでしょうか?
多くの方が「心はある」と思っているかと思いますが、ではそれはどこにあるのでしょう?
この問いは人間がずっと疑問を抱き、ずっと研究されてきました。
歴史を遡れば紀元前3000年頃、古代エジプトでその痕跡を見つける事ができます。
それほど大昔からこの疑問を人間は抱いてきたのです。
歴史における「心」の場所
では、歴史を遡り、「心」がどこにあるのかを見ていきましょう。
紀元前3000年頃、古代エジプトでは「心臓」にあるとされていました。
日本語でも「心の臓器」と書いて「心臓」ですよね。
他にも、紀元前2000年頃、古代バビロニアでは「肝臓」にあるとされていました。
古代ギリシアでは、ヒポクラテスは「脳」にあるとし、プラトンは「脳と脊髄」にあるとし、アリストテレスは「心臓」にあるとしていました。
2世紀になると、ローマ帝国のガレノスは「脳」の中でも「脳室」に心があるとしました。
この説は長く信じられ、17世紀と約1500年間も続きました。
17世紀に入るとデカルトが「松果体」(大脳の第三脳室の後上端壁から後方)にあるとしました。
現代における「心」の場所
このように人間は長い年月をかけて研究を続け、多くの人が仮説を立てて様々な説が今日まで信じられてきました。
そして現代。
「心」とはどこにあるのか。
それは「どこにもない」という結論が出ています。
「心」とは体の場所に存在する物ではなく「脳の活動によって発生する現象である」とされているのです。
しかし、現代科学を持ってしても全貌はいまだに謎だらけでもあります。
今後の研究によってはまた説が大きく変わることも考えられます。
「心」とは何か?

そもそも「心」とはなんでしょう?
まずは定義からみてみましょう。
「心」の定義
少し哲学的な問いですが、そもそも「心」とは何でしょう?
少し考えてみて下さい。
・・・・・・・・・・・・。
考えられましたか?
では、実際のところどうなのかを見ていきましょう。
実は「心」にはちゃんと定義があります。
「心」とは『ヒト特有の精神作用』と定義されています。
精神作用とは
「心」の定義である『ヒト特有の精神作用』
分かるような分からないような微妙な答えですよね。
『精神作用』とは何なのでしょう?
『精神作用』とは、知性、感情、意志などを総合したものを指します。
「知性」とは、物事を理解する能力。
「感情」とは、喜怒哀楽や快不快。
「意志」とは、何かをする意欲や考え。
こうして1つずつ見ていくと分かりやすいですね。
「心」が生まれる仕組み
では「心」とはどうやって生まれるのでしょう?
「脳の活動によって発生する現象である」ということは先ほどお伝えしましたが、具体的にどんな仕組みなのでしょうか。
脳内には約1000億個の神経細胞(ニューロン)ネットワークがあります。
そこに目や耳によって、視覚情報や聴覚情報が電気信号として通ります。
それが脳内の記憶と組み合わさり、それが「心」という現象として生まれるのです。
なぜ「心」があるのか?

「心」はなぜあるんでしょうか?
2つの理由についてみていきます。
「心」がある理由①
人間ほど複雑な感情表現をする生物は存在しません。
これは大脳の前頭連合野の発達が影響していると言われています。
精神活動を司る部位で、この脳部位が大脳に占める割合は
ネコは3.5%・イヌは7%・サルは11.5%・チンパンジーは17%。
そして、人間は29%と非常に発達しています。
それにより、人間は複雑な感情表現を獲得したと言われています。
「心」がある理由②
また、人間という種族が生きていくために、社会的コミュニケーション手段として感情表現が必要だったという背景もあります。
人間は相手の表情や態度から感情を読み取ることで高いコミュニケーションが取ることができます。
それにより、個として脆弱な生物であったとしても、集団としての強さを手に入れたとも言われています。
まとめ

いかがでしたか?
皆さんが何気なく普段しているコミュニケーションや日々感じている感情にも実は様々な背景と歴史があります。
こうした起源や仕組みを知ることでさらに日常でのコミュニケーションを高めて頂ければと思います。