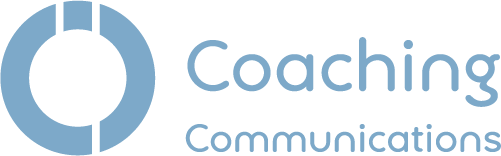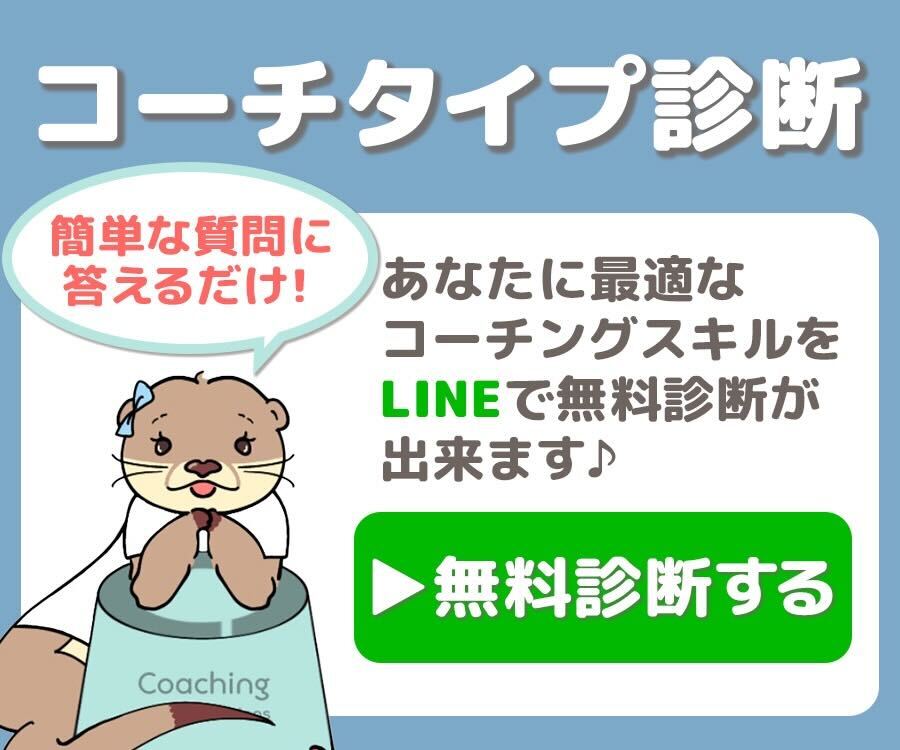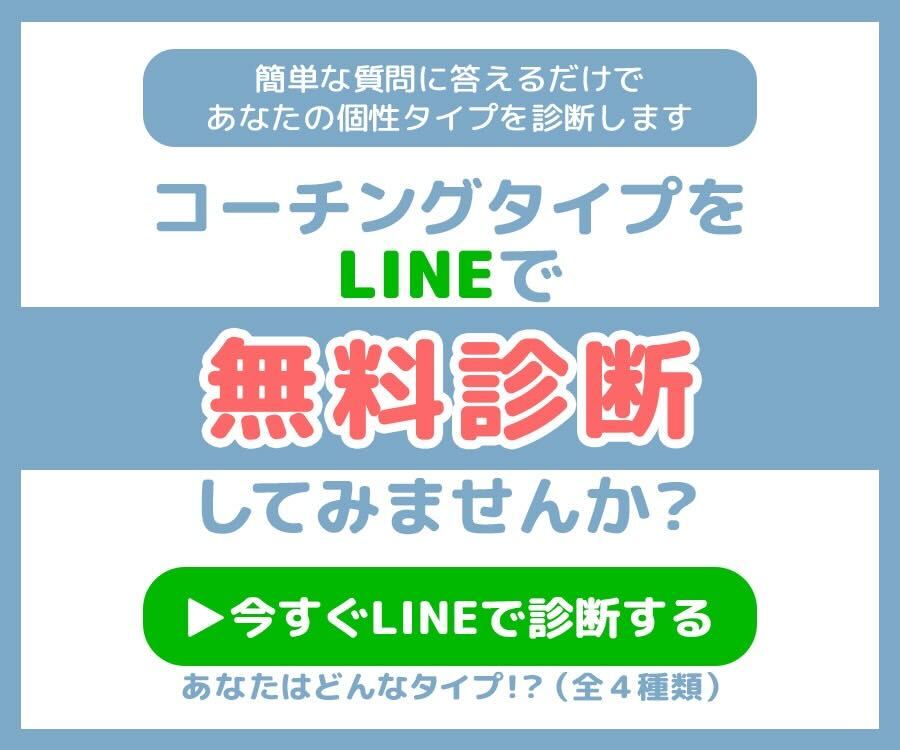保育士はよく「大変な仕事」といわれます。その理由は、悩みの要素が多い職業だからです。
身体的・精神的に未熟な子どもとの関わり、保護者に対する気遣い、女性が多い職場内の人間関係、職場によってはきつい労働条件など、悩みの要素はたくさんあります。
そこでこの記事では保育士がよく抱える悩みを取り上げ、それぞれの悩み対処法についてまとめました。
悩みを抱える保育士さんにとって、役に立つ情報となれば幸いです。
保育士によくある悩み

この章では、よく保育士が抱える悩みについて取り上げていきます。
悩みは大きく分けると以下の5種類に分類されます。
- 子どもに対する悩み
- 保護者に対する悩み
- 職場内の人間関係に対する悩み
- 労働条件に対する悩み
- 自分自身の能力に対する悩み
5種類それぞれ悩みの内容と原因について解説いたします。
子どもに対する悩み
保育園で関わるのは幼児期(年齢でいうと6歳以下)の子どもたちであり、幼児期の子どもは生活力・社会性・精神面など、未熟なことだらけです。
そのため、子どもとの関わりや子どもにかける適切な言葉が分からないと悩む保育士さんは多くいます。
成長発達スピードは子どもによって大きく異なり、1人1人の性格も違います。
保育士はこのような子ども達の個別対応が求められる職業なので、気を遣うことも多いでしょう。
また幼児期の子どもは適切な言葉を選ぶこともできないので、園児同士のトラブルもよく起こります。
保育士が注意をしても、子どもによってはしっかり理解できません。
保育士も1人の人間であるため、言うことを聞かない子にイライラしてしまうなど、子どもとの関わり方に悩む保育士さんは多いです。
保護者に対する悩み
保育士が関わるのは、職員と子どもだけではありません。
子どもの面倒をみる保護者との関わりも多いため、「保護者との関わりが悩み」という保育士さんもたくさんいます。
大人を相手にするサービス業は、基本的にお客様と職場内のスタッフのみの関わりですが、保育士をサービス業に例えるなら、「両親というお客様を相手にする接客業」というイメージです。
子どもと合わせて2人分の相手をしないといけないため、余計な気を遣うこともあるでしょう。
場合によっては保護者からのクレームにも対応しなければなりません。こうした保護者に対しての悩みを抱える保育士も多くいます。
職場内の人間関係に対する悩み
保育士は圧倒的に女性が多い環境で働くことになります。
女性の多い職場で起こりがちな人間関係のトラブルは、「いじめ」「仲間外れ」です。
女性は男性に比べて仲間意識や共感性が強いため、1度人と「合わない」「価値観の違いを受け入れられない」と感じると、いじめや仲間外れが起こりやすいです。
特に園長の権力が強すぎる保育園の場合、園長に気に入られていない部下の保育士はいじめや仲間外れの被害に遭い、ストレスを抱えがちともいわれています。
こうしたいじめや仲間外れが起こる背景として、保育園は1つの組織が小さく人間関係が固定されやすいため、1度人間関係がこじれると、修復するのはなかなか大変だと考えられます。
労働条件に対する悩み
保育士は労働条件がブラックな職場が多いといわれます。
その理由は他の職業に比べて、国からの法律など、従わなければならない制度やルールが多くあるからです。
労働条件に対する悩みを抱える保育士さんも多いでしょう。具体的には以下のような内容です。
- 仕事量と給料が合っていない
- 残業が多い
- 休みが取れない
- 担任制のため、年度途中で退職しづらい
保育士は基本的に人手不足であり、人手不足が故に1人あたりの仕事の負担が増え、さらに退職者が増えるという社会問題を抱えています。
また元気のある子どもたちを相手にするので、ある程度の体力も必要です。
保育園は免疫力の未熟な子ども経由でインフルエンザなどの集団感染症にもかかりやすい環境なため、保育士として働くのに体力・健康面も重要となります。
自分自身の能力に対する悩み
以上の悩みを引き起こす原因が多いため、問題に上手く対処できず自分の能力に対して悩みを抱える保育士さんもいます。
これは特に新人保育士さんに多い悩みです。
- 毎日忙しい生活の中で、次々新しい仕事を覚えなければいけないプレッシャー
- 1人1人個性が違う子どもとの関わり方
- アレルギーや障がいを持つ子どもへの配慮
など保育士は気を遣う場面が多いため、自分自身の能力を不十分と感じやすいのです。
保育士の悩みにおける対処法

続いてこの章では、先ほどあげた5種類の悩みにおける対処法をそれぞれ解説いたします。
悩むことは成長する過程で大切であり、今のあなたにできることを考えて少しずつ行動していきましょう。
子どもに対する悩みの対処法
子どもに対する関わりで大切なのは、「子どもから受けた言葉や態度に対して保育士が反応的にならないこと」です。
子どもは感情のままに言葉を発しますが、裏を返せば「考えが分かりやすい」ともいえます。
そのため、落ち着いて子どもの話を傾聴する姿勢を持つようにしましょう。
子どもの話をよく聴いたうえで言葉を発するようにすると、自然と子どもの態度が落ち着くようになります。
頭ごなしに怒ったところで状況は改善しません。
また「子どもと仲良くならないといけない」と考える保育士もいますが、保育士は子どもと仲良くなる必要はありません。
子どもから信頼される保育士になることと仲良くなることは全く別の話だからです。
「無理に仲良くなろうと頑張らなくていい」と考えられるようになれば、自然と気持ちも楽に働けるのではないでしょうか。
保護者に対する悩みの対処法
保護者との人間関係構築力も、保育士にとっては大切な力です。
保護者は常に保育園にいるわけではないので、保育園に預けている最中の子どもの様子は保育士が思っている以上に気になるものです。
そのため保護者に会う時は元気にあいさつをして、こまめに子どもの様子を報告・相談しましょう。
また保育園には様々なタイプの子どもがいますが、平等に接することで保護者とのトラブルを予防できます。
保護者からえこひいきをする保育士と思われると、信頼を損ねてしまうため注意が必要です。
万が一クレームが来た場合は、話をしっかり傾聴する姿勢も大切です。
職場内の人間関係に対する悩みの対処法
職場内の人間関係における悩みは大きなストレスとなるため、対処法を知っておきたいところです。
保育士に限らず人間関係が発生する職場では、先輩から怒られたり、理不尽な対応をされることもあるでしょう。
人間である以上、きっと嫌な気持ちになると思います。
そんな時に「相手がなぜその言葉を発したのか」を立ち止まって考える習慣がつくと、人間関係におけるストレスが減ります。
同時にあなた自身の伝え方を見直すことも大切です。
「物事がうまく伝えられなかった」「相手を怒らせてしまった」などの反省から、伝え方を振り返る習慣をつけましょう。
労働条件に対する悩みの対処法
労働条件における悩みは、正直個人の努力では解決できないこともあるでしょう。
将来的に労働条件が改善されないと予想される場合や、やりがいよりも労働条件に関するストレスの方が大きい場合は、転職や働き方を見直すことが必要かもしれません。
近年保育士としての働き方は多様化しています。
正社員だけでなく非常勤や派遣という働き方もありますし、職場によって労働条件は大きく異なります。
労働条件に不満がある場合は、単に「現在の職場があなたの望む働き方に合っていないだけ」という可能性もあります。
ぜひ1度保育士としての働き方について考えてみてください。
自分自身の能力に対する悩みの対処法
能力に関する悩みの対処法としておすすめなのは「過去の自分と比べて成長することを目標にする」ことです。
保育士は専門職であるため、つい他の同期と比べてしまう気持ちも分かりますが、他人と自分を比較して悩むのは、あまり生産的ではありません。
そして過去の自分と比べるうえでも、完璧を目指さないことが大切です。
保育士の仕事をしていると、予測不能なことはしょっちゅう起こります。
臨機応変な対応を求められるうえに、自分の努力ではどうにもならないこともあります。
そのため完璧主義にならず、「1か月前と比べて、〇〇ができるようになった」など、少しでも自分の成長があれば十分頑張っていると捉えることも大切です。
まとめ
以上、保育士がよく抱える悩みとそれぞれの対処法についてまとめました。
保育士はストレスの多い職業ですが、「子どもの成長を間近で見られて社会貢献をしている」という大きなやりがいもある仕事です。
現在悩みを抱える保育士さんにとって、この記事が参考となれば幸いです。
もしどうしても自分1人で悩みと向き合うのが辛い方は、悩み解決に効果的なコーチングの体験会もあります。
ぜひ、こうした機会を利用されてみてはいかがでしょうか?