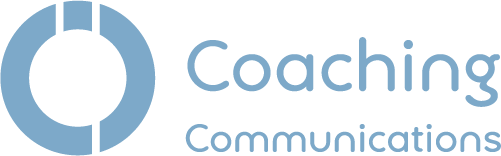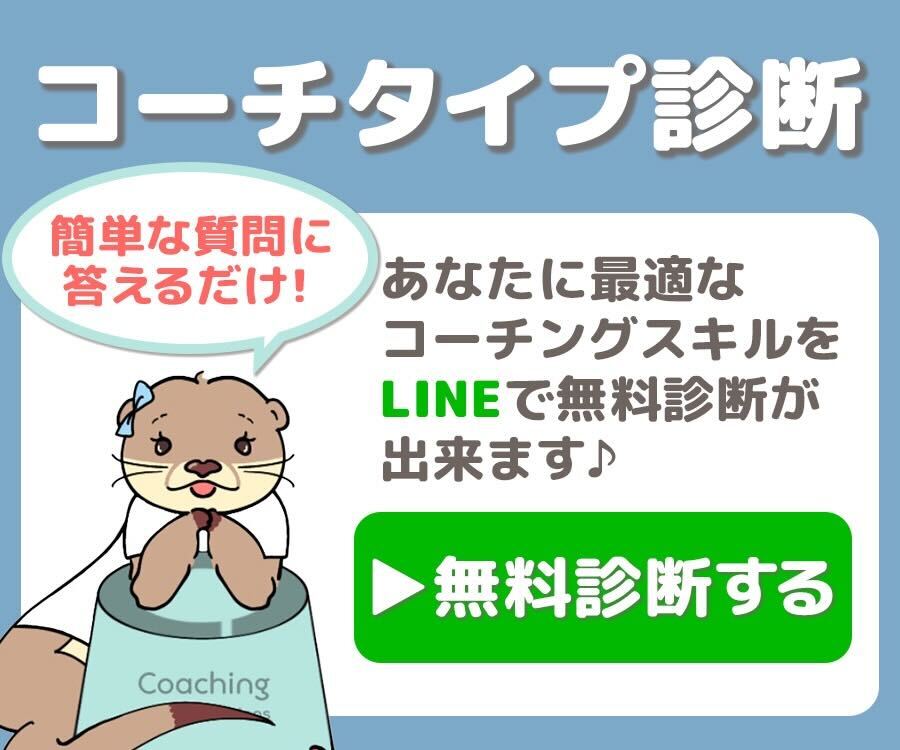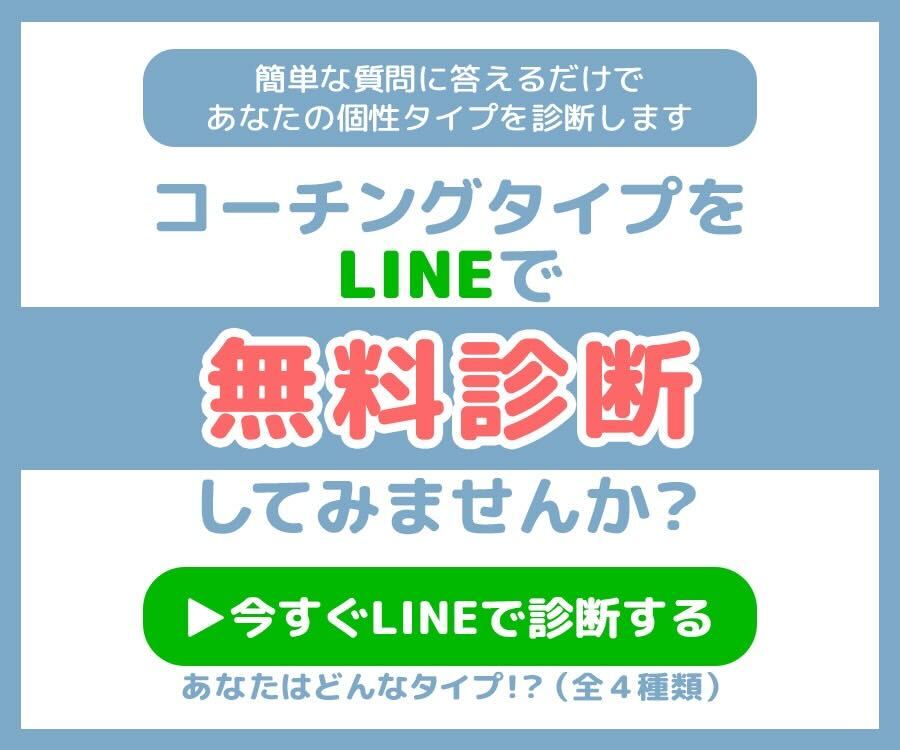高校生のお子さんを持つ保護者で「子どもとの関わり方で悩んでいる」という方は非常に多いです。
高校生が直面する思春期の時期は子どもと大人の間に立っている時期であり、身体的にも精神的にも急激な変化が訪れます。
この急激な変化に対応しきれず高校生自身が悩むことも多いですし、それを見守る保護者にとっても悩みの多い時期となります。
そこでこの記事では、高校生のお子さんを持つ保護者さん向けに「高校生(思春期)の精神的状態」「保護者が悩みがちなこととその理由」「高校生の子どもとの関わり方で大切なこと」について解説します。
現在悩んでいることがスッキリし、お子さんとの関わり方を考えるうえでのヒントになれば幸いです。
高校生(思春期)の精神的状態

高校生(思春期)の時期は精神状態にも特徴があり、大きくは以下の2点です。
- 多感でメンタルが不安定になりがち
- 精神的に自立する時期
多感でメンタルが不安定になりがち
高校生は身体の成長に対して心の成長が追いつかず「メンタルが不安定になりがち」な時期です。
小さいことで喜びを感じたり、ひどく傷ついて落ち込んだりと気持ちの変化が激しいことが特徴です。
異性への興味が強くなるでもこの時期であり、まだ精神的に成熟していない者同士の恋愛は、数多くの悩みを抱えることでしょう。
また高校生は友達の影響も受けやすい時期です。
親よりも友達付き合いを優先しがちなため、保護者との衝突も多くなります。
精神的に自立する時期
一方でこの思春期の時期を過ごすからこそ「精神的に自立して大人に近づく」ともいえます。
高校生活までは、ある程度限られた選択肢の中で生きてきた人が多いでしょう。
しかし高校を卒業した後は、「進学するのが就職するのか」「実家暮らしを続けるか1人暮らしを始めるか」などをはじめ、人によって進路やライフスタイルが大きく分かれます。
そしてこの選択の多くは高校生のうちにしておかなければならないため、「将来何をするか?」という今後の生き方や、「自分はどんな人間か?」といった現在の自分とひたすら向き合う時期となります。
多くの高校生はこの時期を過ごした後に、親から精神的自立ができるようになります。
高校生の子どもを持つ保護者の悩み

高校生(思春期)の特徴をご理解いただいたところで、次は「高校生の子どもに対する保護者の悩み」に触れていきます。
よく見られる悩みは以下の3つであり、その理由やおすすめの対処法についてもご説明します。
- 子どもとの喧嘩が増えた
- 子どもの将来が心配
- 子どもが勉強に無気力
子どもとの喧嘩が増えた
高校生になると「喧嘩をすることが増えた」と悩まれている保護者さんは多いです。
高校生になるとアイデンティティ(自我)が形成され始め、自分の生き方や軸が徐々に定まっていきます。
まさに親からあれこれ口を出されたり、干渉されることを嫌う時期です。
そのため、保護者との衝突が増えるのは仕方がないことかもしれません。
保護者自身も、事あるごとに「受験が近いんだからしっかり勉強しなさい」「進路についてちゃんと考えなさい」などと言われれば、不快な気分になるのではないでしょうか?
親から見ると、子どもに対してつい否定的なことを言いたくなるかもしれませんが、それだけでは子どもと衝突してしまいます。
親が意見しても子どもが受け入れてくれる姿勢を作るには、日頃から承認することも大切です。
子どもが「自分のことを分かってくれている」と思えると、お互いにストレスの減った状態で生活ができるようになります。
子どもの将来が心配
先ほど「高校生は生き方や進路など、決めなければならないことが多い」と書きました。
そのため日々将来について悩んでいるのです。
しかも毎日の高校生活の中では、大学生や社会人と接する機会も少なければ、勉強や部活に追われて将来についてゆっくり考える機会も少ないのが現実です。
将来像がはっきり決まっている子どもの方が少数派でしょう。
親から見ると子どもの将来を不安に感じるかもしれませんが、まだ明確に決まっていないだけであって、案外自分の人生を真剣に考えている子どもは多いものです。
子どもの将来を考えるのであれば、日頃から子どもとの対話を繰り返すことが大切です。
何気ない日常会話からヒントが見つかり、子ども自身に考えるきっかけを与えることができます。
子どもが勉強に無気力
勉強熱心な姿勢を持っている子どもは、保護者から見ると安心できる存在でしょう。
しかし、そんな子どもは少ないのが現実です。勉強に価値を感じられない高校生の方が圧倒的に多いでしょう。
大学受験を志していたとしても、「他に目指すものがないから仕方なく勉強している」という高校生も多いです。
しかし高校生活で大事なことは、何も勉強する事だけではありません。
もし子どもが勉強することに意欲を感じられないなら、「何か別の目標を持てないか」「興味のありそうなことは何か」を保護者と一緒に探すことも大切です。
100%自分のことを理解できている人間はいません。他人からの意見をもらって気がつくこともたくさんあります。
それは高校生の子どもに限らず誰にでもいえることであり、保護者自身も意識する必要があります。
高校生の子どもへ精神的自立を促すための関わり方

高校生の子どもを持つ保護者は、最終的に「精神的自立をしてほしい」と思っている方が多いです。
この章では「子どもへ精神的自立を促すには、親がどのように関わったら良いのか」についてお伝えします。
自分の人生は自分で決めてもらう
高校生ともなれば、基本的に「自分の人生は、自分で決めてしっかり責任まで取る」という姿勢を持つことが大切です。
これは言い換えると、「親の意見を押し付けない」「干渉しすぎない」ということです。
もしあなたが子どもに対して「大学に行って大手企業に就職してほしい」と思っていたとしても、それを子どもに伝えるのは得策ではありません。
なぜなら親から指定された人生を歩むことほど、自己責任のマインドは育たないからです。
意見をするのはいいと思いますが、最終的な決定事項は子ども自身でしてもらうようにしましょう。
「メタ認知能力」を育てる
子どものメタ認知能力を育てることも大切です。
メタ認知能力とは「自分の思考や行動パターンを客観的に把握できている状態」のことを指します。
先ほども少し書きましたが、自分で気づけないことはたくさんあります。
そのためには人との対話が必要です。対話を繰り返すことで、同時に自分のことを振り返るきっかけになるからです。
対話の中では、積極的に子どもの意見を聴くことを心がけましょう。
自分で考えさせるきっかけを与えることで、子ども自身のメタ認知能力をより育てることができます。
まとめ

この記事では、高校生のお子さんを持つ親御さんにとっての悩みと、その悩みを解決するためにおすすめな関わり方について解説いたしました。
お子さんへの関わり方で取り入れられそうなものがありましたら、ぜひ1つでも実践してくださると幸いです。
もし「自分では子どもとより良い関わりができるか心配」「もっと子どもと良好・円満な関係を築きたい」という保護者の方は、1度コーチングの体験会に参加されてみてはいかがでしょうか?
良好な人間関係を築き、相手の成長を引き出す対人能力として、近年コーチングスキルは非常に注目されています。
興味のある方はぜひお問い合わせください。